東 直子×山崎ナオコーラ対談「昔も今も、子育てについて考える」

歌人、作家の東直子さんによる子育てエッセイ『一緒に生きる 親子の風景』の刊行を記念して、月刊雑誌「母の友」(2022年5月号)で、作家の山崎ナオコーラさんとの対談を行いました。
『一緒に生きる』は、「母の友」の連載がもとになった本ですが、連載開始時、東さんの二人の子どもはすでに成人しており、子育てを終えてからの“子育てエッセイ”でした。当時の自分に語りかけながら書いていたという東さんと、価値観が目まぐるしく変わる今、現役で子育てをしている作家の山崎さんとで、子育てについてのあれこれを語ってもらいました。対談記事を、再掲してお届けいたします。
社会の中の子育て
山崎ナオコーラさん(以下山崎) “育児エッセイ”をご自身で書きたいという気持ちはあったのでしょうか?
東 直子さん(以下東) 子どもが生まれてから短歌を始めて、さらに長い文章を書きたいという気持ちはありましたけど、生まれてすぐのころは、子どもを育てるということは自分の作家としてのキャリアを止めることだという意識がありました。でも、そのうちに、出版社の方から子育てについて書いてくださいと言われるようになって、あ、子育てもキャリアになるんだと気づいたんです。
山崎さんは、社会との関わりの中での子育てというものを、すごく意識されていますよね。
山崎 私は三十代後半に一人目の子どもを産んだので、自分の中で割と“社会欲”があふれてきているときで。だから、“社会の中で子育てをするということ”を強く意識していたんだと思います。
東 私は、二十三歳で結婚してすぐに子どもが生まれたので、そういう意識があまりない中で子育てが降りかかってきたという感じでした。
山崎 育児をしているときに、展望というか、こういう育児をしようとか、こういう子に育てたいとか、先のことは考えていらっしゃったんですか?
東 理想みたいなものはなんとなくありました。でも、そううまくいかないですよね。上の子が生まれてすぐに下の子も生まれて、上の子は繊細でよく泣く子で大変だったんですけど、下の子は全然違うタイプで、多少放っておいても大丈夫。結構いたずらをするけど、よく食べてよく寝る子なので手はかからなかった。このまま大きくなるのかと想像していたんですけど、成長するにつれて逆転してきて、下の子の方が繊細になっていきました。
私は中学生のころに出会った『大草原の小さな家』(アメリカの作家ローラ・インガルス・ワイルダーの書いた家族史小説)が好きで、家族同士が信頼し合っていて、みんなりっぱで、あんな風な家庭が理想としてあったんですけど、現実は全くそうはいかないし、ローラのお母さんみたいに、冷静で優しいお母さんでいたいという気持ちはあっても、現実は(笑)。常に焦燥感のようなものはありました。
幼稚園くらいまでは、子どもも常に親と一緒で、親子の世界に何か他のものが入ってくるという感じはしないんですけれど、小学校、中学校、高校と大きくなるにつれて、子ども自身が社会的な生き物になっていくと、だんだんつらくなっていった感じはあります。子どもが社会的な関わりの中で優劣を付けられるというか、比較されながら生きていかなければならなくなることで、いろいろ揺れる部分があったなと。
山崎 それは、子どもだけではなくて、親もということですか?
東 はい、そうですね。例えば学校で、他の子はできているのに、あなたの子はできていませんと言われることってあると思うんです。そういう、社会的にこうあらねばならないという制約が与えられることによって、親子関係って揺れてしまう。すごく切ないことですけれど。
“母”という役割
山崎 東さんご自身は、学校に馴染める子どもだったんですか?
東 全然(笑)。友だちもあまりいなくて、修学旅行でグループ組んだりしますよね。そういうのに入れなくて、余った人とグループ作ってました。
山崎 私も全然学校に馴染めなかったから、子どもが今年小学生になって、それがすごくこわいんですよね。幼稚園では子どもは自由に遊んで、やりたいことをさせてもらえていたけれど、小学校に上がると、ルールとか集団行動とか、急にたくさんの制約が課されるじゃないですか。
東 息子の小学校の入学式の日が大雨だったんですけど、そんな中で校長先生が、「はい、みなさん、これから九年間の義務教育の始まりです」って宣言されて、すごく気持ちが重くなったのを今でも覚えています(笑)。でも、私が子育てをしていた二十年ほど前に比べると、今は学校も社会もずいぶん変わってきたようにも感じますけれど。
このコロナ禍でもすごく価値観が変わりましたし、私が「母の友」で連載をしていた六年間でも、母や父といった“役割”のようなものの価値観も変わってきたなと思いました。山崎さんと白岩玄さんとのご著書『ミルクとコロナ』(河出書房新社)でも書かれていましたけど、共働きが増えて、母親も父親もフルタイムで働きながら子育てをしていて、そんな中で、父親に向けられた“育児参加”みたいなもののつらさも感じるのですがどうですか?
山崎 今は、SNSなどがあって、文章を書くときに、書いた人が何者なのかとか、それをどの程度やっているのかとか、当事者なのかとか、そういうことをジャッジされますよね。昔だったら、どんな立場でもよくて、とりあえずいい文章を書けばよかったというところがあった気がしたんです。昔の文学者なんかはもっと無邪気に批判されそうなことでも書いていますよね。だけど今はまず、「お前はどうなんだ、どんな立場で言ってんだ」みたいなことを言われてしまう。育児の話をしたとすると、「じゃあお前はどの程度育児をやってんだ」というところから始めなければいけないっていうことが結構ありますよね。
東 子ども一人ひとり性格も状況も違うから、育児といっても正解は一つじゃないですよね。だから、育児していない人の育児への見解もどんどん語ってほしいなって思うんです。“子どもを産んだことがないので育児を語る資格はありません”みたいな感じになってしまうのはよくないなと思っているんです。子どもを産んだり、子育てをすることがこわいという人が結構いると思うんですけれど、確かにこれだけネガティブな情報があると先を心配してしまうのかもしれないですよね。私は何も考えずに子どもが生まれてしまったので、子育てを今の人ほど自問自答しながらせずにできた気がしますけど、いろいろ考えすぎると産めなかっただろうなって。
山崎 育児していない人の育児の話って、私もすごく聞いてみたいです。お母さんにしても、例えば二十点の育児しかできていませんて人でも、堂々と語っていい社会にしたいですよね。今は、「ある程度がんばっているけれど、〇〇が大変です」みたいな言い方をしなくちゃいけない雰囲気がある。「努力もしてないですけど大変です」では聞いてくれない世の中だなって。でも、がんばっているかがんばっていないかっていう評価をなしにして話せるといいなって思います。
東 そうですよね。なぜか育児に関しては、責任問題みたいなことと同等になっていて、山崎さんもエッセイで書かれていたけど、例えば虐待事件とか起きたときに、親がとにかく非難されますよね。でも親だけの問題じゃないんだろうなと私も常々思っていて、社会に追い詰められたという側面もありますよね。
山崎 東さんは、「母」という言葉をどう捉えていらっしゃいますか?
東 そんなに特殊な言葉としては捉えていなくて、自然な言葉として捉えていました。産むということは明らかに母親にしかできないことで、でも母性神話のようなものにはずっと疑問を持っていました。
山崎 東さんのこのエッセイの中に、「子育ては、実は本能ではなく、理性と知性でコントロールするものなのです」という一文があって、本当にそうなんだよなとすごい腑に落ちました。母親業って何も考えずにできるって思われがちな気がするんです。でもみんな考えて考えてやっているから、こういう風に言ってもらえて気持ちがすっとしました。
東 私もこれを書きながら気が付いたというところがあって、本能でできるもんだと思い込むとうまくいかないんですよね。自分は大人で社会的な人間であると、ちゃんと理性的に考えて行動した方がうまくいくような気がします。理性的に役割を与えられて役者が演技するように、今やらなければいけないことを考えると、その方がやりやすい。
山崎 そうですよね。仕事の場合でもそうですけど、考えてもうまくいかないこともあるし、本能とか、生まれたら自然になれると思われてしまうと、母親失格とか人間失格みたいな気分になってしまうから、育児は考えて考えてやる作業なんだって思ってもらいたい。
東 子育ては、生まれつき誰もができるものでもないということなんですよね。
※お二人には、他にもいろいろ語ってもらっています。この続きは、単行本『一緒に生きる 親子の風景』に収録されています。
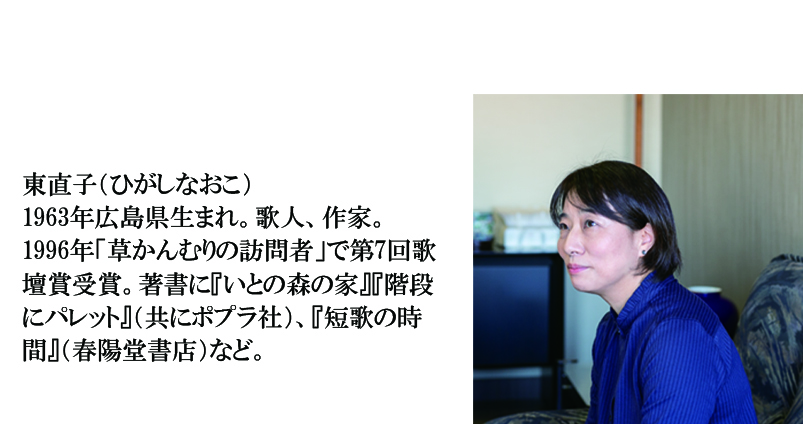
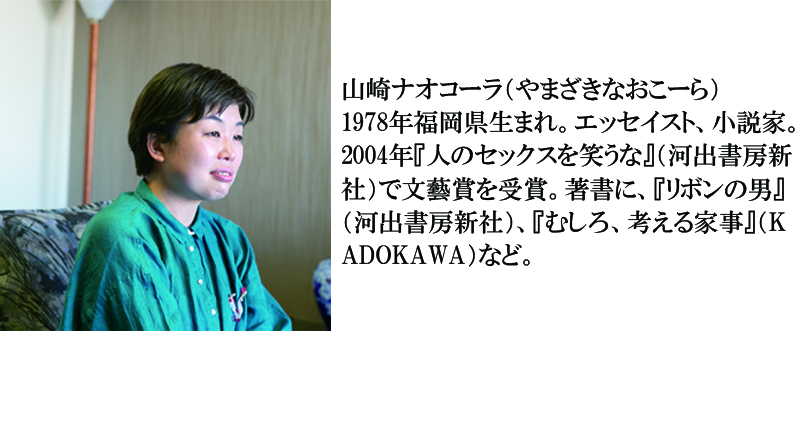
2022.05.06










